第38回 渋沢・クローデル賞
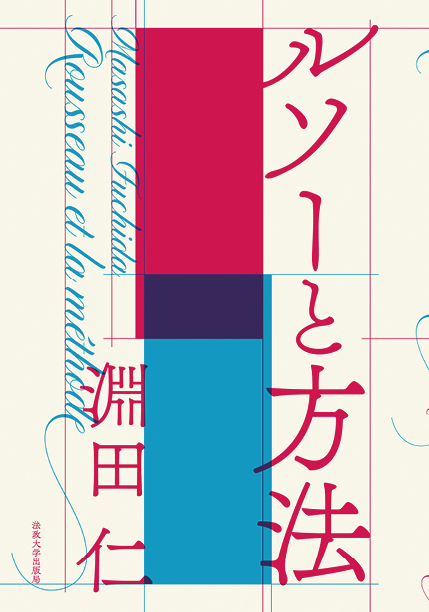
奨励賞
淵田 仁 氏
『ルソーと方法』
法政大学出版局、2019 年

福井県出身。1984年生。城西大学現代政策学部社会経済システム学科助教。横浜市立大学商学部を卒業後、一橋大学大学院社会学研究科にて博士(社会学)取得。18世紀フランスの哲学・思想史が専攻。主な著作として『ルソーと方法』(法政大学出版局、2019年)がある。共著に『百科全書の時空──典拠・生成・転位』(法政大学出版局、2018年)、『〈つながり〉の現代思想──社会的紐帯をめぐる哲学・政治・精神分析』(明石書店、2018年)等。
受賞者の言葉 |
ルソーについて何かを書くというとき、私はつねに「いまさら」と感じてきた。ルソーについてこれまで膨大な研究が上梓され、戦後日本では民主主義を基礎づけるためにルソーが読まれ、そして白水社『ルソー全集』が1984年6月完結し、その二ヶ月後に生を受けた私がルソーを初めて手に取った大学三年生当時、ルソーはある意味役割を終えた思想家であるように思われた。遅れてやってきたという自覚をもっていた私は、ルソーをどう読めばいいのかという問題につねにつきまとわれていた。 『ルソーと方法』あとがきにも記したように、本書の成立は偶然の産物である。先行者たちの論文や研究書に出逢いながら、彼ら/彼女らの仕事とともに歩みを進めた結果でしかない。振り返れば何がしかの必然を感じないこともないが、それは事後的なものでしかない。 しかし、『ルソーと方法』が示しているのは、こうした偶然の歴史をどうルソーが記述しようとしていたのかということではないか。18世紀フランスというメディア化しはじめた世界のなかでルソーは自らの思考を他者に開示する〈仕方〉にこだわり続けた人であった。ゆえに、私は何を言ったかよりもどう語るかというパフォーマンス的な側面に光をあて、ルソーを読み解くことにした。だがやはりこの書を書く間、ルソーの思想ないしは思想という行為全般を侮辱することになるのではないかという気持ちを私はつねに抱いていた。真摯に語る人間に対してその語りを分析することはその者を愚弄することと同じではないか、と。こうした両義的な気持ちで書き続けられた書が『ルソーと方法』であった。今回の受賞を受けて、この複雑な気分から少し解放された気がした。 この場を借りて、いまは亡き恩師である古茂田宏先生に感謝の意を申し上げたいと思います。先生が若書きで書かれたルソーの論文を、先生と出会う前に私が偶然読んでしまったことから本書が構想されたと言っても過言ではありません。図書館に眠っている知は確実に後世に繋がっていく。こうした知のリレーに私も貢献するべく、今後も研究に励みたい。 そして審査委員ならびに関係者のみなさまに厚く御礼申し上げます。渋沢・クローデル賞奨励賞を賜ったことに心より感謝いたします。 |
選評 |
評者 川出 良枝(東京大学教授) ルソー「の」方法ではなく、ルソー「と」方法。この表題は、本書にこめられた著者の重層的関心をさりげなくも端的に表現している。 著者はまず、ルソーがいかなる学問方法論をとるにいたったかを緻密に分析し、18世紀フランスにおける哲学的方法の問題圏にルソーを位置づけ、さらには方法という観点から、啓蒙哲学のアポリアを逆照射する。こうした正攻法の手法による研究として、本書の学術的価値は高い。だが、著者の関心はそこにとどまらない。そうした「方法」をとることで、フィロゾーフたちが作り上げた支配的言論空間において、ルソーが自らの作品をどう戦略的に表出したか、というメタレベルの分析にまで筆が及ぶ。方法を嫌悪していると述べながら、方法にのっとった作品であることを偽装するルソー。「山師のやり口」とルソー自身が呼ぶ方法の意味を探ることも本書の課題の一つである。 何しろ、対象は、国内外を問わず、膨大な研究蓄積のあるルソーである。既存の研究の成果を十分踏まえ、そこに何ものかを新たに付け加える作業は、実に根気のいるものであったであろう。本書はその点で、きわめて堅実であり、これまでルソーの分析的方法に対する懐疑として言及されてきたものの実体が、コンディヤック経験哲学における分析方法に対する批判であることを説得的に明らかにした。真理の発見を分析ではなく、「内的感覚」という主観的な感覚に求めるに至ったルソーが、それを実践すべく苦闘した作品が、『人間不平等起源論』に他ならない。ルソーが安易な「分析」の罠に陥らないように、独自の歴史叙述を展開した経緯が、あたかもルソーの思考の流れによりそうかのような迫真のテクスト分析によって明らかにされている。 また、ルソーの初期著作『化学教程』やビュフォンの『地球論』からの影響の指摘など、現在の18世紀研究の領野の広がりが巧みに織り込まれているところも心憎い。さらには、方法をめぐるルソーの葛藤が、彼の一連の自伝的諸著作にどう反映しているかを分析する章も用意されるなど、清新な労作である。 とはいえ、著者の重層的関心が、本書をかなり複雑な一冊としたことも事実である。作品論としては物足りず、また、様々な要素が随所で錯綜し、筋を追うのに苦労するという感想をもつ読者もいるかもしれない。また、ルソーがいかなる方法を退けたのか、という点は分かるが、ルソーの方法が何であり、どういう意義があったのかはz必ずしも十分説明されていないのではないか、といった疑問も選考会では提起された。 だが、いくつかの課題はあるにせよ、本書がルソー研究の新たな可能性を感じさせる意欲作であることに変わりはない。 |


