第40回 渋沢・クローデル賞 奨励賞
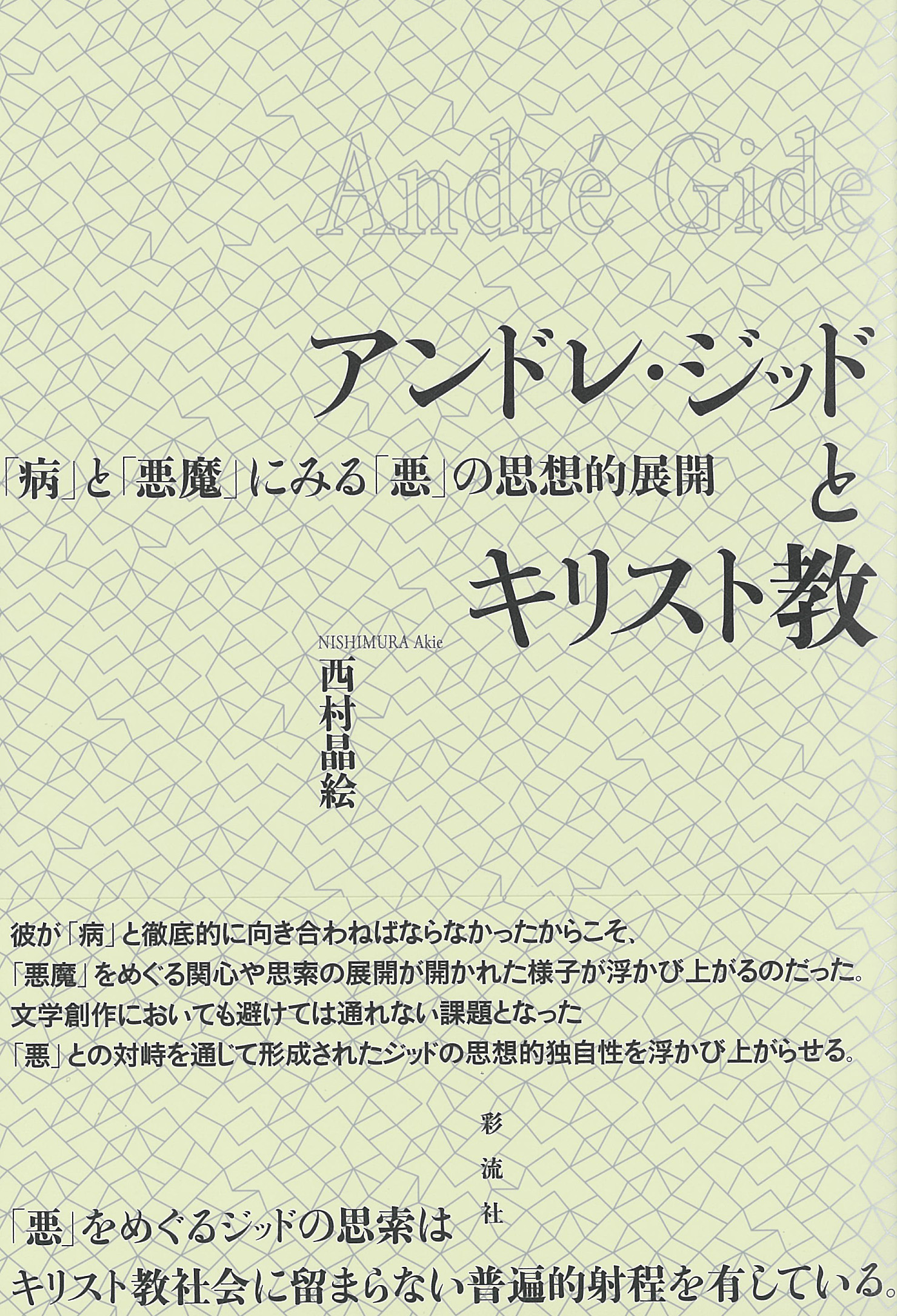
奨励賞
西村 晶絵 氏
『アンドレ・ジッドとキリスト教―「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想的展開』
彩流社、2022年

東京都出身。2018年、東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程単位取得満期退学。2020年、同大学院にて博士号取得〔博士(学術)〕。
大谷大学真宗総合研究所東京分室PD研究員(2019年度)、盛岡大学文学部助教(2020年度-22年度)を経て、2023年4月より静岡県立大学国際関係学部講師。専門はアンドレ・ジッドを中心とした19世紀後半から20世紀前半のフランス文学。
受賞者の言葉 |
第40回渋沢・クローデル賞奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。ご選考くださった先生方ならびに関係者の皆様、これまで様々なかたちで導いてくださった先生方、本書に関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。 思い返せば本書は、学部生時代に生じた「宗教によって人間は不幸になることがあるのに、なぜ宗教は存在し続けるのか?」という素朴な問いから出発したように思います。1年生の時に読んだ遠藤周作の『沈黙』は、私にこのような疑問を抱かせました。キリシタン禁制の時代、「転ぶ」ことを拒否したキリシタンたちは、拷問にかけられ殉教していきます。にもかかわらず、神は沈黙し続けるのです。また、これら「強き人」ではなく、拷問や死を恐れて神を裏切る「弱き人」に焦点が当たっている点も印象に残りました。当時の私には、クリスチャンの作家でも護教論を書くわけではないということが、とても意外でした。 その後、学部での交換留学中にジッドの『狭き門』の原書を読んだ際、遠藤の作品に通じるようなキリスト教への問題意識を感じました。信仰によってもたらされる悲劇という点が重なるように思われたのです。 また、やがて芽生えたもう一つの関心に、芸術と医学、芸術家と病の関係がありました。大学院生時代に留学先のパリでノルダウの『退廃論』の存在を知り、医学者が当時の芸術家たちを病的とみなし、彼らの作品を論拠に論証しようとしたことの面白さに惹かれました。私にとってのこれら二つの関心の接合を試みたものが、本書ということになります。 執筆に際しては、19世紀や20世紀の文学が現代とどのようなつながりを持ちうるかという点を意識してきたつもりです。図らずもこの数年、新たな感染症の流行で、世界中の人々の日常が「病」と隣り合わせのものとなりました。また昨年は、新興宗教に起因する事件により、日本社会の宗教問題が顕在化しました。本書で論じた内容から推測するに、もしジッドが今生きているとすれば、実生活ではコロナに怯えつつも、この病に振り回される人間こそを「病的」な存在として描いたように思われますし、信者に金銭を要求し、周囲の人々をも不幸にする宗教団体に対しては、厳しい非難を向けるでしょう。一人の作家の思索を追った本書が、特定の時代・地域・宗教についての関心を超え、現代社会を見つめ直すわずかな契機になりうるとすれば嬉しく思います。 |
選評 |
評者 伊達聖伸(東京大学教授) 本書は、重要ながらも近年ではそもそも読まれ論じられることが少ない作家アンドレ・ジッドにおける「病/悪」と「悪魔」を関連づけ、セクシュアリティと宗教の観点からおもな作品を読み解く研究である。第一部では、ジッドが「病」を克服する――向き合い方を覚えて肯定する――過程で独特の宗教観が築きあげられるようになって様子を描いている。第二部では、見ること(voir)と知ること(savoir)を「盲目」と「宗教」の問題に絡める『田園交響楽』などを論じる一方で、『法王庁の抜け穴』を素材としたカトリック風刺を分析し、またジッドが同性愛とキリスト教のあいだにどのような折り合いをつけたのかが論じられる。第三部は、複雑な『贋金使い』における「悪魔」の問題が「病」や「宗教」や「神」の問題につながっていることを、ジッドのウィリアム・ブレイク論やドストエフスキー論を手がかりに論じる。『贋金使い』を「宗教」の観点から読み解くことは自明ではないと思われることからも、著者の努力と苦労が忍ばれる。文章自体は読みやすく、ページをめくるにしたがって引き込まれる。 その一方、審査委員の間では、ジッドの宗教観を論じるのに『狭き門』に触れていないのは欠落ではないか、カトリックとプロテスタントの理解が図式的にすぎるのではないかといった指摘があった。評者自身も、著者がジッドのテクストを同時代の医学言説との関わりにおいて社会史的・文化史的な観点から明らかにすると述べているにもかかわらず、必ずしも社会史的・文化史的背景が丁寧に説明されているわけではなく、やや肩透かしを食う思いをした。また、ジッドという作家を今日改めて取りあげて論じるに当たり、セクシュアリティと宗教がアクチュアルだからというのを自明の前提とするのではなく、なぜ日本においてジッド(とりわけ『狭き門』)がある時期までよく読まれ、その後読まれなくなっていったのか、それに対して本書がどのような位置づけにあるのか、その立場を明示的に示してもらいたかった。 そうすれば、先行世代と著者の問題意識の違いがどこにあるか、ひいては、今後日本においていかなるフランス文学研究がありえるのか、そのときジッドという作家はどのような形で現代の私たちに訴えかけてくるのかといった一連の大きな問いが拓かれるだろう。本書はその端緒を秘めた著作と言えよう。大作家ジッドの初期から円熟期までの作品群を取りあげ、複雑なテーマにまとまりをつけることのできる視座から議論を一貫させて、ひとつの明快なジッド像を提示したことは高く評価される。 |


