第40回(2023年度) 受賞作品
|
|
該当無し |
|
|
|
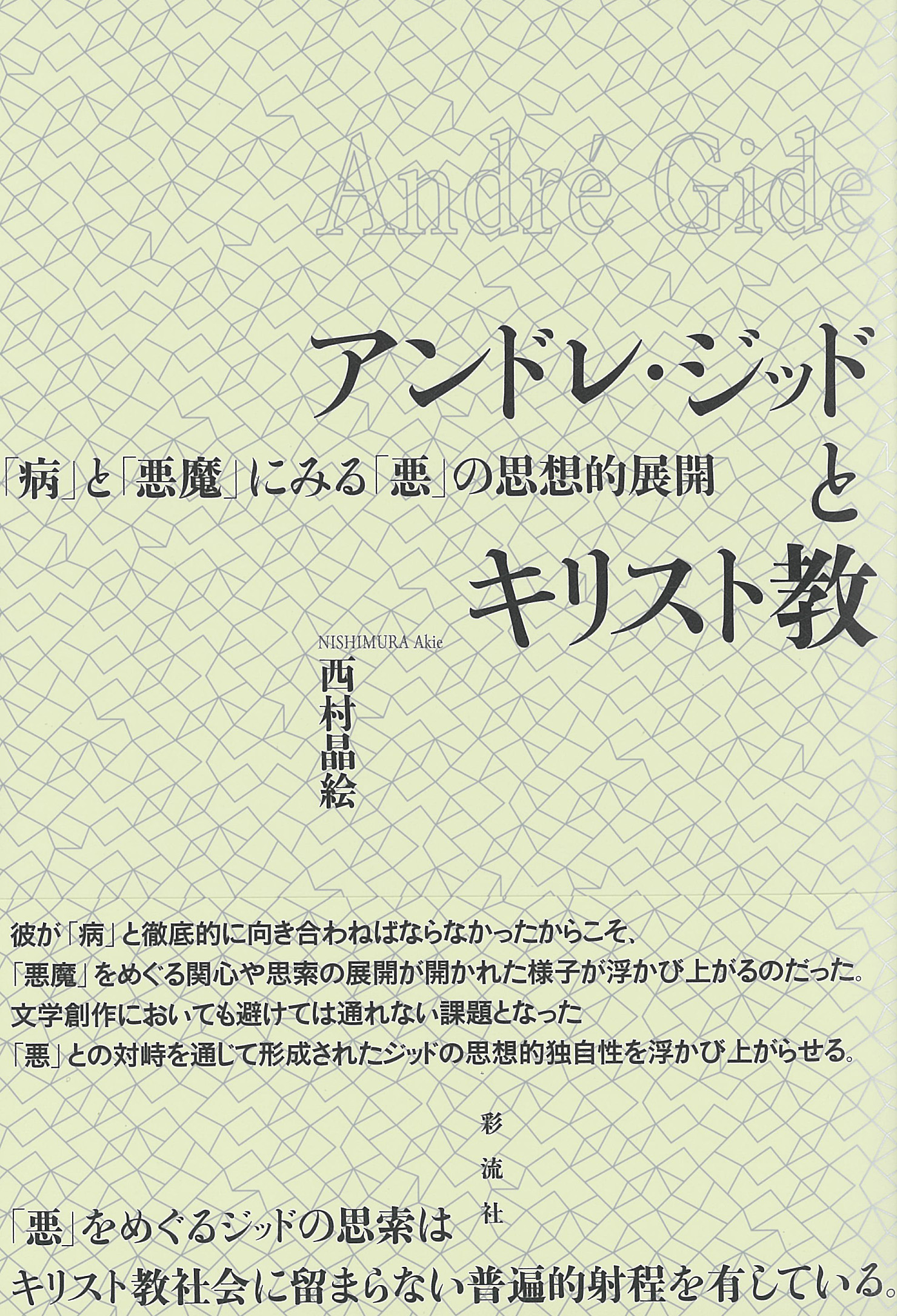 |
西村 晶絵 アンドレ・ジッドとキリスト教―「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想的展開 彩流社、2022 |
|
|
 |
佐藤香寿実 承認のライシテとムスリムの場所づくり―「辺境の街」ストラスブールの実践 人文書院、2023 |
|
|
 |
アルチュール・デフランス 奈良時代の詩歌文学:中国文学の再創作と日本文学の創作の間 博士論文 |
審査報告
公益財団法人日仏会館
渋沢・クローデル賞委員会委員長
中地 義和
今年第40回を数える渋沢・クローデル賞は、外部専門家の評価を含む第1次審査、渋沢クローデル賞委員会内部の第2次審査を経て、本賞なし、奨励賞2件という結論に至りました。奨励賞2作の間に評価の優劣はありませんが、日仏会館の慣例に従い、名字のアルファベット順にご報告します。
一番目は、西村晶絵さんの『アンドレ・ジッドとキリスト教―「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想史的転回』(彩流社、2022年)と題された著作です。ジッドはプロテスタントで同性愛者、当時のフランスにおいては宗教とセクシュアリティの両面でマイノリティでした。これが彼の文学を根底から規定しているのですが、西村さんは同性愛以前の「病=悪」として幼いジッドが抱えていた自慰癖から筆を起こします。そしてほぼ時系列に沿ってジッド作品を読み解きながら、宗教的「悪マル」とされる種々の誘惑や欲望を「病マル」と結びつけて描くジッド初期の作品は当然ながら暗鬱で、人物たちは容易に充足を見出だせないことを指摘します。しかし1890年代の二度のアフリカ滞在を機に、ジッドはキリスト教が悪であり罪とする同性愛を「自らの自然」として引き受け、一つの個性として解放しようとしたと著者は考えます。しかもキリスト教信仰の内側からそれを揺さぶるプロテスタント(抗議者、反抗者)としてそうするのです。アフリカ旅行を転機とするこの「病」からの回復が、本書の第一の論点です。第二の重要な論点は「悪魔」です。ある時期からジッドの作品に頻出しはじめる「悪魔」とは、著者によれば、外在的な人格ではなく、「個々人のなかに存在する誘惑するもの、精神的な弱さや迷いの比喩」なのですが、「病」からの回復以後のジッドは、ブレイクの『天国と地獄の結婚』に触発されて、「「悪魔」を通じてこそ、初めて神へと至る可能性が開かれる」「美しい感情によって悪い文学が作られる、悪魔の協力のない、本物の芸術作品はあり得ない」、「聖人のなかに芸術家は存在せず、芸術家のなかに聖人はいない」といった考えに立つようになります。ジッド最後の大作『贋金使い』の主要人物の一人ひとりと「悪魔」との関係を、ドストエフスキーと比較しながら犀利に分析した第3部が本書の白眉をなしています。
このように西村さんの受賞作は、「病」と「悪魔」を両輪に据えて、ジッドにおける「悪」の問題の独特の展開を探るものです。構想の明快さと合わせて特筆すべきは、軽快な文章、読みやすさです。多くの審査員がこの点を評価しました。
ジッドの文学・思想の内的読解としては、一貫した包括的展望を示すことに成功しており、立派な成果であることは間違いないのですが、審査会では留保も表明されました。第1に幼年期の「病」をめぐる医学的言説の引用はあるものの、文化的社会的な受け止め方の紹介を予告しながら行なっていないではないかという不満です。第2に、ジッドの代表作である『狭き門』への言及が皆無なのはなぜかという疑問です。第3は、ジッドのアクチュアリティの問題です。一時期プルーストと並び称されたジッドが脚光を浴びなくなってから久しいのですが、この優れたジッド研究を公刊された西村さんにとって、ジッドの今日的意義はどこにあるのかを説く一章を設けてもよかったのではないか。たしかに「結論」の末尾で少し触れてはおられますが、もう少し正面からこの点を論じるページがあれば、いっそう幅のある魅力的な成果になったのではないかと思われます。
二つ目の奨励賞受賞作は、佐藤香寿実さんの『承認のライシテとムスリムの場所作り「辺境の町」ストラスブールの実践』(人文書院、2023年)です。
近代のフランスは、国民各自の自由と平等を保障する前提として、政治・行政・教育といった公共空間から宗教性を払拭する政教分離を推し進めてきました。この原則は「ライシテ」と呼ばれ、近年研究が活況を呈している分野です。ところが、出自や信仰を捨象した「抽象的な個人としての市民」から構成される共和国モデルが依拠する普遍主義はしばしば、移民を含む構成員が体現する文化の多様性を顧みない排他的な力として働き、「自由・平等・友愛」の実現には不十分であることが広く認識されるようになりました。そうした齟齬が危機的な形で露呈するのは、大半がイスラム教徒(ムスリム)である旧植民地からの移民とその子孫の同化・統合の問題においてです。
フランスが抱えるこの難題に風穴を開けるためのヒントを秘めた試みとして、佐藤さんは、ストラスブールという一都市における「承認のライシテ」、つまり共和国の抽象的な普遍主義に逆行するように、多様な「宗教が公共的役割を担うことを積極的に承認するライシテ」の試みに着目します。
本書は2部立てで、第1部は文献に基づく理論的研究です。フランス共和国の普遍主義的なライシテが、多元的社会の出現とグロバリゼーションの趨勢のなかでますます激しい軋轢を生む経緯が、法制度の沿革、ムスリム統合政策の変遷、さらには西欧における「ムスリム」の想像的表象まで含めてダイナミックに考察されます。それと対照的に、独仏間で何度も帰属が変わった歴史のせいで、アルザス=モゼル地方、なかでもその中心地ストラスブールでは、1905年の政教分離法が例外的に適用されず、1801年にナポレオンとローマ教皇の間で結ばれた政教協約(コンコルダ)が今なお宗教政策の基盤を成し、カトリックをはじめとする公認宗教以外の非公認宗教も排除されることなく、ムスリム団体間でも異なる宗教間でも比較的友好的な関係が築かれ、多様性、多元性を許容する歴史的風土が独特のライシテを生み出したことが、克明に跡づけられます。
第2部は、ムスリムを柔軟な形で社会に包摂するためにストラスブールで試みられた三つのユニークな取り組み——大モスクの建設、ムスリム公共墓地の建設、宗教間対話の促進——が、現地調査と当事者たちへのインタビューをふんだんに交えながら考察されます。「承認のライシテ」には「テロリズムの防波堤」(330)の面があり、市当局からの資金援助には政治権力にとって望ましい特定の宗教団体を選別する面が不可避であるといった負の側面の明晰な認識も欠けておらず、また第1部の理論的考察との整合性も十分に図られています。EUの本部があるストラスブールは今やヨーロッパの中心といえますが、本書では「辺境」と呼ばれ、その地方都市におけるローカルな試みが、ムスリムを包摂する多元的な場所の創設を通して、フランスという国の未来の設計に大いなる示唆を与えうることを、共感を持って語るこの第2部にこそ本書の真価があると言えます。
ただ、審査会ではいくつかの方法論的留保が表明されました。
まず、第2部のベースをなすインタビューの有効性についてです。佐藤さん自身も「結び」で正直に告白されているように、ここに再現されたインタビューは、ムスリムの指導的立場の人々が団体の意向を表明している面が強く、平均的なムスリムの考え方・感じ方を掬い取っているとはみなしにくいという点です。
第2の留保は、「承認のライシテ」のモデルとして取り上げられるのがストラスブールの一例にとどまる点です。事例研究としてはやはり比較項がほしいところです。
しかし留保は留保として、本書は独自の発想から推し進められたオリジナリティの高い研究で、未来への有益な提言となりうる部分を含んでいます。奨励賞にふさわしい成果であることは揺るぎません。
以上が審査報告です。お二人の研究のさらなる展開を期待いたします。


